ニョメン・オーガナイジング⑯「食」というコミュニティー作り/文・イラスト=張歩里
2025年10月01日 08:18 ニョメン・オーガナイジング「食」によって作られる
ひとは食べたものでできている。あたり前かもしれないが肌も、髪も、骨も、内臓も、血液も、私たちの体は全て、口にしたものからできている。
第一子の子育てのときから、初めてスーパーで食品表示を見たりし、食べ物の身体への影響を気にするようになった。しかし3人目となるとどっこい、口に入るものを気にしだすときりがないことを知ったし、目が回る忙しさのなか「無添加・手作りを心がけましょう」なんて文句をみると、罪悪感ばかり膨らむ毎日である。
健康といっても、体質・生活習慣・食事のバランス・ストレス環境など、複数の要因が複雑に絡み合っているだろうし、今までのライフステージで直面してこなかった「家族の健康管理」という新しい項目に、日々悩んだり、諦めたり、翻弄されている読者も少なくないだろう。
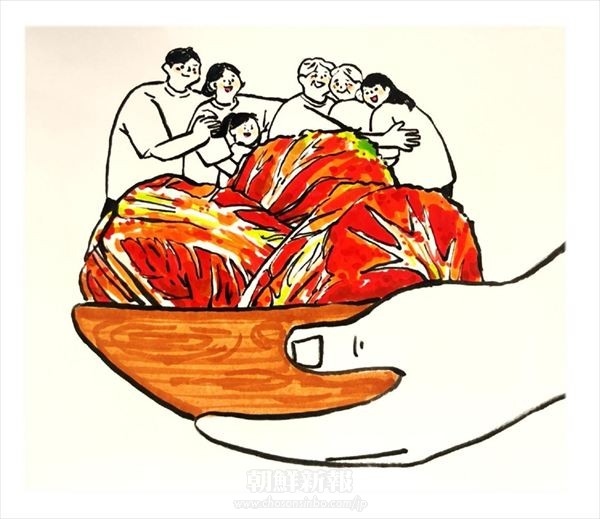
私自身も最近、買い物に行ってカゴの中を見たら、買っている野菜がいつも同じことに気が付いたのだ。そりゃ今や、ハウス栽培が浸透しているし、品種改良もされ、栽培技術が上がっているのだから一年中、同じ野菜が食べられるようになった。しかし子どもたちは一つひとつの作物に、旬があることなんて知らないだろう…。
思えば私は幼少期、春になるとオモニに連れられてニョメンのオルシンたちとよく、山菜採りに行った。新鮮なタンポポの葉の爽やかな苦みや、軒先で天日干しされカラカラになったワラビを不思議に見ていた記憶が鮮明に残っている。
体が求める栄養は、その時期の旬の作物に多く含まれるというが、私の身体もこのような在日朝鮮人女性たちが貧しい中で育んだ知恵と工夫、大きな愛情によって作られてきたのだろう。そう、ひとは食べたものでできているのだから、同胞社会も長年かのじょたちが「創造」してきた「食」によって作られているのかもしれない。
同じコミュニティーという証
ニョメン活動と向き合おうとすると、「食」という営みは切って離せないだろう。
在日朝鮮人が向けられてきた差別、そして貧困と過酷な労働のなかで、在日朝鮮人女性は家族や親族、トンネの食をどのように賄い、腹を満たしてきたのだろうか。
1世のハルモニたちが家事や育児を担いながらも、日銭を稼ぎ、また一方では在日朝鮮人女性の開放のため奔走した当時、かのじょらはどうやって材料を調達し、いつ調理をし、提供したのか、それを想像することは、自分に連なる在日朝鮮人女性の経験と向き合うことでもある。
また私たちが食べてきた食材や料理の記憶について語ると、そこには必ず在日朝鮮人女性の姿が思い返されるだろうし、さまざまな地域のあらゆる生活や経験が紡がれるはずだ。
今でも同胞訪問でオルシンの家にあがりキムチやニンニクの匂いがプーンとすると、懐かしくほっとした気持ちになる。ハルモニの家や、ハッキョの調理室もこんな匂いだったなあと思いだし、自分はやっぱりこういう環境で育ったんだなと再確認したりもする。
生まれ育った地域でなくでも、在日朝鮮人コミュニティーの「食」は時代や場所を超え、他者との信頼や連帯感を象徴し、同じ体験を共有していることの証にもなっている。
今も慶弔にかかわる行事で料理をこしらえたり、ハッキョに寄付するため数十キロのキムチを漬けたり、同胞行事でチジミや煮込み料理を販売したりと、ニョメンの中心活動には「食」がある。
もちろんそれに負担を感じる人もいるだろうし、家父長制や性別役割分業を問うことも忘れてはならない。しかし在日朝鮮人運動において歴史的に「食」はシンボリックな意味を持ってきたのだから、その根幹を担ってきた女性たちの労力と献身を忘れてはならないはずだ。
「食」は単なる栄養摂取事そのものを超えて、同胞コミュニティーの人間関係を形成し、維持し、発展させてきた最も強力な社会的行為だったのではないか。まさに「食」は命に直結する。
「ご飯、食べた?(밥 먹었나?)」という朝鮮語の挨拶が、これからの同胞社会においても、根強く定着してほしいものだ。
これからも「食」を真ん中に
数年前のコロナ禍、ニョメンから届いた手紙とささやかな「食材」には、届けてくれた、渡してくれたという物語がプラスされ、自分の生活の中に、そういった物語がどれほどあるのかと考えるだけで、気持ちが支えられた。今では子どもたちの通学バスを通じて、オモニたちは、食材を分け合ったり、タッパーや鍋まで行き交う。
私はニョメン活動で食事やお茶(お酒)がどんなに大切で、一緒に食べることで気持ちが緩んだり、心が開いたりするのを何度も目にし、経験し、「食」の持つ力を感じてきた。
若いニョメン世代にとって「調理する」という行為はまだまだハードルが高いかもしれないし、子ども連れだと参加しづらいこともある。しかし調理する人以外にも、子どもと遊ぶ役割が必要だし、その場にいて知っている料理の知識を教えあったりするのも立派な「食」というコミュニティー作りだ。
これからも「食」を真ん中に、それぞれの地域同胞のなかで育まれた食文化を身体に取り込み、そのコミュニティーへの愛着とともに誰もが健康で、命を大切にする同胞社会を作っていきたい。咀嚼・分解・吸収をへて、朝鮮人そのものになっていくだろうから。
(関東地方女性同盟員)
※オーガナイジングとは、仲間を集め、物語を語り、多くの人々が共に行動することで社会に変化を起こすこと。新時代の女性同盟の活動内容と方式を読者と共に模索します。
(朝鮮新報)




 ニョメン・オーガナイジング⑮チームで乗り越える名もなき仕事/文・イラスト=張歩里
ニョメン・オーガナイジング⑮チームで乗り越える名もなき仕事/文・イラスト=張歩里  ニョメン・オーガナイジング⑭「選挙ヘイト」の中で暮らす/文・イラスト=張歩里
ニョメン・オーガナイジング⑭「選挙ヘイト」の中で暮らす/文・イラスト=張歩里 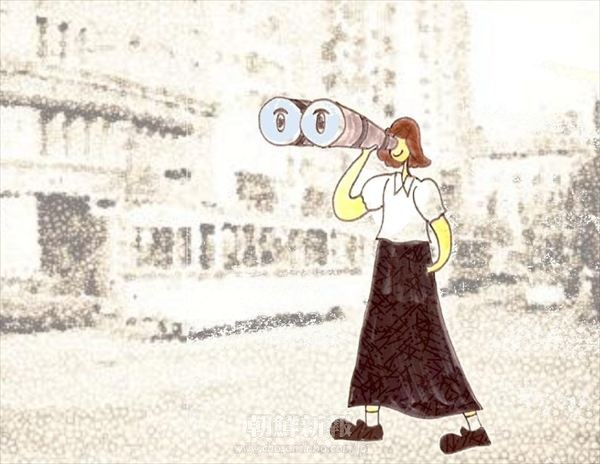 ニョメン・オーガナイジング⑬ニョメン結成世代に学ぶ/文・イラスト=張歩里
ニョメン・オーガナイジング⑬ニョメン結成世代に学ぶ/文・イラスト=張歩里