
朝高生の大学入試問題
2021年11月12日 09:55
毎日新聞が大学入試問題と関連し5日、「朝鮮学校生の資格審査見直しを」という記事を掲載した。朝鮮学校の生徒には出願前に個別の「入学資格審査」が課せられていること、一部の大学で推薦入試による朝鮮学校の生徒…
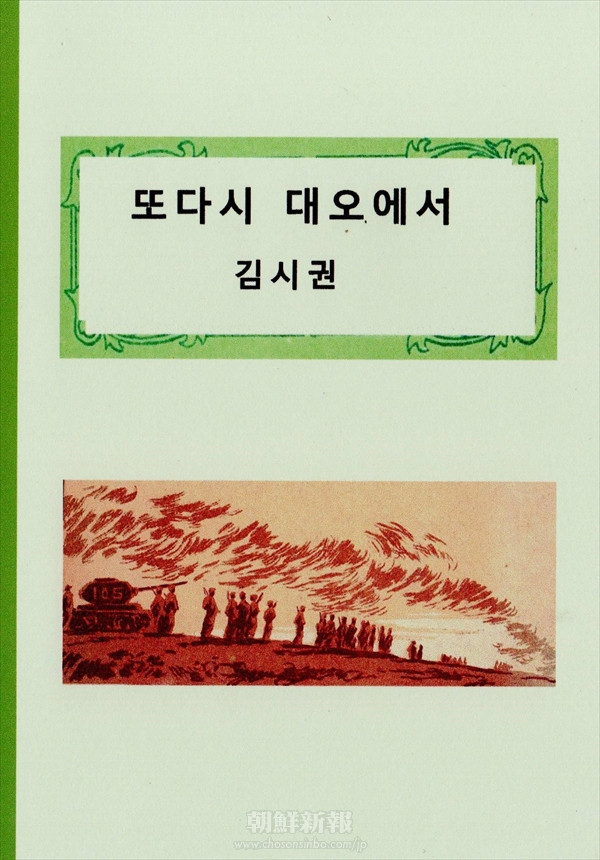
〈読書エッセー〉晴講雨読・金時権『ふたたび隊伍にて』とクォン・スンフィ女史/任正爀
2021年11月12日 08:12

【寄稿】“福岡初級の子どもたちにお芝居を届けたい”/深水登志子
2021年11月11日 09:00

12月12日は「快勝」の日
2021年11月10日 13:31
「ウリ民族フォーラム2021 in 東京足立」の開催まで、残すところちょうど一カ月となった。実行委員を務める足立地域青商会のメンバーたちは、本番に向けた準備に拍車をかける一方で、地域同胞社会の発展のた…

〈学美の世界 35〉世界ができ上がっていく過程/河美香
2021年11月08日 11:24
中学生の作品を見るのが、好きだ。 中学生の作品を通して、会ったこともない作者の悩みや希望、作品を作っている時の表情なんかも想像してしまう。 「思春期」とか「中二病」と一括りにしてしまえばそれまでだが、…

〈春・夏・秋・冬〉元山市にストーカー?
2021年11月08日 09:38
目立つ靴、新しい形の靴を履いている人を見かけては追いかける人が、江原道・元山市に出没しているという。立ち止まってもらい靴の図案を描いては立ち去るそうだ ▼労働新聞10月26日付に掲載された、このストー…

〈民族教育と朝鮮舞踊10〉「在日朝鮮学生中央芸術競演大会」
2021年11月06日 07:50
舞踊部(ソジョ)活動の大きな目標 「在日朝鮮学生中央芸術競演大会」は今年で53回目を迎えた。1963年に第1回が開催され、65、66、74、76、78年度は中央大会を行わず、地方大会のみであったり実施…

選挙
2021年11月05日 09:02
10月31日、衆議院議員選挙の投開票が行われた。各局の速報番組を観るのが好きで今回も8時から見ていた。自民は大きく議席数を減らすという予想もあったが、単独で過半数を確保し自公連立政権が続くこととなる。…

祖国の姿/姜詩那
2021年11月02日 13:41
これは私が見た祖国の風景の話。 祖国の道には、花が咲いている。賑わう道にも、人気がない道にも、一直線の道にも、曲がりくねった道にも。 開城に向かうバスの中。眠りに落ちそうになっていたとき、パッと目が覚…
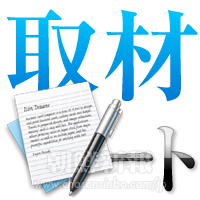
「実り」の季節
2021年11月01日 11:13
先日、長野初中から本社宛に贈り物が届いた。中身は約20年の歴史を誇る同校の「学習田」で、日本の支援者たちの協力のもと、子どもたちが収穫した真っ白な新米だった。



