ニョメン・オーガナイジング⑪同胞「コンノリ」をスケッチする/ 文・イラスト=張歩里
2025年04月30日 14:38 ニョメン・オーガナイジング「コンノリ」という風景
年度が変わって様々な物事が新たなスタートを迎える「春」は心躍る季節である。
冬が去ってポカポカと暖かくなる季節ということもあり、お花見は同胞にとっても春の代表的なイベントとなっている。春の嬉しさを感じながら、支部や分会の同胞と食事やお酒を楽しむ宴会は格別!
そもそもお花見というイベントは、日本特有の文化というが、在日朝鮮人社会でも「꽃놀이(コンノリ)」文化は各地で育まれてきた。
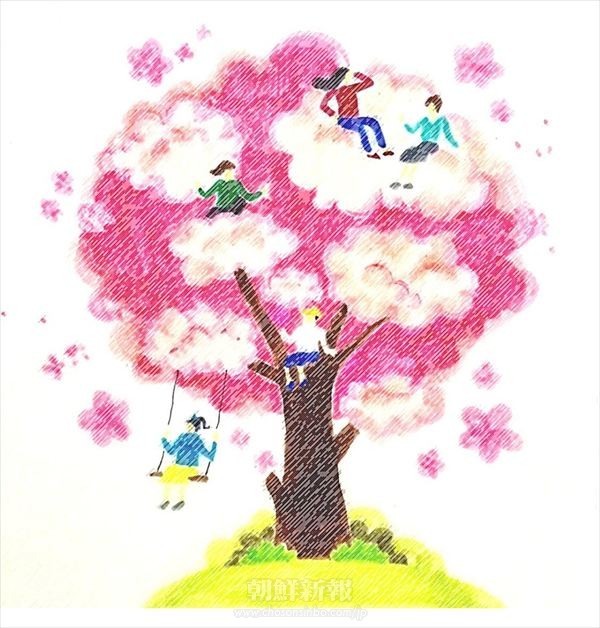
桜は古くから日本の国花として認識されてきたし、可憐に咲き乱れるも豪快に散っていく桜の運命を「人生の儚さ」に例えたり、現世に執着せず、義のために命を捧げるという「武士」の理想になぞらえたり、「サクラ」にはいわゆる日本人の美学や価値観が反映されていることを、同胞たちも知らないわけではない。まして植民地統治時代には日本の文化的影響力の強化と、日本帝国主義の領土拡大と正当性を示す手段として、朝鮮に大量に植えられたこともある。
しかし、桜の木の下でお弁当を広げ、団欒を楽しむ日本人をよそに、同胞たちは七輪を囲み、もくもくの煙のなか、焼き肉やキムチを食べたりする。昔は歌や民族楽器まで登場することもしばしば。文化のハイブリディティともいうべきか、日本のなかで生活を送りながらも、日常とは区別されるところに在日同胞独特な文化を持っているのだ。
私自身もこれが幼いころから見慣れた光景であるので、支部、分会の「原風景」として記憶されている。結婚して出身地ではないところで暮らし始めたが、やはり同じ同胞文化を経験し、共有していることにふと、気づく。それに花見客をよくみると家族や同僚、同年代の仲間が多いようだが、こちらは0歳から80代までとその年齢の幅も、まぁ広い。一見共通の話はなさそうだが、あらゆる世代が一つの輪になって話に花を咲かせているのだ。
日本文化的な空間ではあるが、ここに「参加」することでやはり同じ記憶や経験をもつ共同体であるのだと再認識する。
心に刻まれる「味覚の記憶」
「花より団子」、朝鮮語では「금강산도 식후경(金剛山も食後景)」と言うそうだが、おいしい手料理やお酒を飲むのがコンノリの醍醐味だ。もちろんニョメンオルシンたちは朝鮮料理を持ち寄り、お手製のサムジャンにご飯を包んで若い子たちの口まで運んでくれたりもする。
やはり食べ物は、同胞の共有する記憶・経験という点でとても重要な部分なので、格別なこだわりが現れる。
こんな大きなタッパーをなぜ持っているのだろうと思うが、手製のパンチャンたちが一気に配られる。一方われわれ若手世代はカラフルなサラダや、パパッと作れる一品、それに子どもが好きそうな有名スーパーの人気惣菜を添える。
「味覚の記憶」というものがあるそうだが、それは食べ物の香りを含んだ空気が鼻に移動することによって風味となり、それに対し脳が反応することでおこるらしい。また、10歳頃までの味の記憶がその後の味覚の基礎をつくるそうだ。
「コンノリ」ならではの「味覚」経験が、同胞から愛された記憶として私たちの幼い心に刻まれ、同胞トンネの「原風景」として焼き付いているのかもしれない。
もちろん私の子どもたちも、春の香りと朝鮮パンチャンが入り混ざったこの嗅覚や味覚の「記憶」が、後の人生をより豊かなものにしてくれると信じているし、これからもこの時間を楽しみに、大切にしていきたいと思うのである。
「心配り」あってこそ
「コンノリ」でいつも一番感心するのはニョメンイルクンらの「気配り」である。
子どもたちのお菓子や飲み物はもちろん、食後のコーヒー(しかも温・冷選べる!)、デザートまで準備してくれている。それにご高齢のオルシンはレジャーシートに座るのが辛いからと、ふかふかの座布団や折り畳み椅子まで用意してあるのだ。若輩ものの経験では膝の痛みまで配慮できない。イルクンたちがいつも同胞のそばで苦しみや喜びを分かち合っているからこその「心配り」なのだ。
このような温かい気遣いがあるからこそオルシンたちは口々に「元気に生きて、またこうやって来年も集まりましょう!」と約束しあうのだ。
そうやって満開の桜の下で笑い合う同胞の姿をみると、30代最後のニョメン活動のスタートに、素敵な一歩が踏めたような気がする。
(関東地方女性同盟員)
※オーガナイジングとは、仲間を集め、物語を語り、多くの人々が共に行動することで社会に変化を起こすこと。新時代の女性同盟の活動内容と方式を読者と共に模索します。



