〈記者らが記した歴史の瞬間⑥〉勝利のその日まで/日本各地で行われた高校無償化裁判
2025年11月24日 06:30 民族教育絶対に諦めない

東京無償化裁判の地裁判決を報じた2017年9月20日付の新報
2010年度からスタートした「高校授業料無償化・就学支援金支給制度」、通称・「高校無償化」制度。当時の民主党政権の目玉政策として実施され、当初朝鮮高校も無償化の対象に含まれていた。しかし同年の延坪島砲撃事件(11月23日)などを理由に朝鮮高校適用に関する審査が凍結され、審査再開後も結論が出ないまま自民党政権に移行した。そして第2次安倍政権は、発足後真っ先に朝鮮高校が対象となる根拠規定(ハ)を削除する前代未聞の省令改悪をはたらき、朝鮮高校のみを無償化の対象外とする異例の措置をとった。
ここから今に至る長い「無償化闘争」が始まった。朝鮮学校関係者や同胞たちは2010年から日本各地で無償化適用を求める記者会見や街頭宣伝、集会、要請活動を展開。東京や大阪では大規模なデモ行進も行われた。「朝鮮新報」は無償化適用のために声を上げる朝鮮学校の生徒、教員、保護者、そして日本の支援者らの声を紙面に載せ、日本政府の差別の不当性を伝え続けた。
記者らの行動の根底には、「運動を広めるのも狭めるのもメディアにかかっている」という共通意識があった。朝鮮学校関係者の声、「自分たちの権利は自分たちが戦い抜いて勝ち取るしかない」という訴えは、全同胞に当事者としての意識を持たせる起爆剤となった。
そして2013年1月から大阪、愛知、広島、福岡、東京の各地5カ所の朝鮮高校に通う生徒や卒業生らが原告となり、国を相手取る裁判が始まった。5か所の地域で行われた口頭弁論の回数は地裁と高裁を合わせて114回にも及んだ。
朝鮮学校への不当な差別を是正するために、大阪では、朝鮮学校関係者、支援する会、弁護士ら三者の呼びかけで「朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪」(「無償化連絡会・大阪」)が結成され、2012年4月17日から大阪府庁前での街頭宣伝「火曜日行動」をスタートさせた。東京では、朝鮮大学校の学生たちの呼びかけにより、2013年5月31日から「金曜行動」が始まった
「一日も早く『火曜日行動』を終わらせよう」
「差別のない社会こそが正義」
「後輩たちには同じ苦しみを与えたくない」
無償化裁判の口頭弁論が行われている間も記者たちは、朝鮮学校関係者の声を届けた。
無償化裁判は、2017年7月28日に大阪地裁判決で全面勝訴を勝ち取ったものの、1年後の控訴審判決で逆転敗訴。約8年半に及ぶ司法闘争は、2021年に広島で学校側の上告が棄却されたことによりすべての地域で原告敗訴が確定し、終結した。
判決直後、結果を待つ聴衆を前に、法廷から出てきた原告側弁護団が掲げた「不当判決」の旗だし。「ふざけるな」「司法がそんなことをして恥ずかしくないのか」「恥を知れ」
各地では敗訴の一報に、悲鳴、怒号、落胆の声が後を絶たなかった。そして「朝鮮学校を差別するな」とシュプレヒコールを叫び続け、「声を集まれ、歌となれ」を合唱する地域もあった。
東京での無償化裁判を取材した月刊「イオ」の韓賢珠記者(当時は「朝鮮新報」の記者)は、「大阪地裁での全面勝訴もあり、集まった同胞たちの表情は期待と緊張が入り混じっていた。不当判決が出された瞬間の担当弁護士や朝鮮学校関係者の様子をリアルに、余すことなく伝えることで、世論を喚起し、いかに理不尽な判決が下されたのか、同胞のみならずこの社会のマジョリティである日本の人々までもが問題意識を育むような報道を心掛けた」と当時を振り返った。
民族教育史に刻まれた新たな1ページ

勝訴を勝ち取り喜びをかみしめる弁護団(大阪)
15回にわたり行われた裁判のうち、唯一勝訴したのが大阪地裁での判決だ。1年後に控訴審で1審勝訴を取り消す不当判決が下されるも、大阪で勝ち取ったこの貴重な「1勝」は朝鮮学校に通う子どもたちの未来の一筋の光であることに今も変わりない。
2013年1月24日に愛知とともに提訴に踏み切った大阪では、国を相手に大阪朝鮮学園が原告となり行政訴訟を起こした。提訴から4年。16回に及ぶ口頭弁論を経て、2017年2月に結審を迎えた。
そして2017年7月28日、大阪地裁は学園側の請求を全面的に認め、国の処分を取り消し、無償化の対象とするよう命じた。
判決では、「母国語と、母国の歴史および文化についての教育は、民族教育にとって重要な意義を有し、民族的自覚および民族的自尊心を醸成するうえで基本的な教育というべきである。そうすると、朝鮮高級学校が朝鮮語による授業を行い、北朝鮮の視座から歴史的・社会的・地理的事象を教えるとともに北朝鮮を建国し現在まで統治してきた北朝鮮の指導者や北朝鮮の国家理念を肯定的に評価することも、朝鮮高級学校の上記教育目的それ自体には沿うもの」と朝鮮学校の民族教育権を認めた。
判決が出た瞬間、傍聴席は歓喜に包まれた。弁護団が「勝訴」、「行政の差別を司法が糾す」を持ち笑顔で裁判所から出てきた。地裁の外で待機していた朝鮮学校の関係者や支持者たちはその旗を見て、一様に抱き合い、涙を流し、大歓声を上げた。
大阪地裁での勝訴を2017年8月4日付の新報は「民族教育の歴史をふまえて朝鮮学校の教育の自立性を認めた画期的なもの」だと報道した。
その後行われた判決報告集会(7月28日、東成区民センター)では、大阪朝高(当時)の女子生徒が発言した。かのじょはこの日のために、もしもの結果も想定して2つのシナリオの原稿を書き上げていた。思いをこめて徹夜の末に完成させた原稿は、半分以上を消しゴムで消すはめになってしまった。そのときの心境を問うた記者の質問に対し、かのじょは「最高の気分です」と満面の笑みで答えた。

勝訴の喜びを爆発させるオモニたち
大阪の無償化裁判を取材した李永徳記者は、「長い裁判闘争の過程で関係者の間には疲れも見えたが、同胞や良心的な日本市民らの強い信念が司法を動かし、民族教育史に新たな1ページを刻んだ。民族的権利の擁護、獲得に注がれる諦めない気持ちこそが社会を変え、歴史を作るのだと強く実感した」と当時を振り返った。
そして、「差別や排除を乗り越え、明るい未来を拓こうとする強い意志を広く発信し、読む者の心を動かす報道こそが、現実を変える力となる。記者は、単なる出来事の記録者ではなく、人々の心をつなぎ、民族教育権擁護運動のうねりを生み出す当事者でもある」と語った。
歴史的な大阪地裁判決、それに歓喜する朝鮮学校関係者、保護者、日本の支援者らの姿から記者はこれからの朝鮮学校と民族教育の明るい未来を肌で感じたことであろう。そして当時の記者たちは、いつかは「高校無償化適用実現」、「長年の夢かなう」といった表題の記事を書きたいと強く願ったはずだ。
日本司法の不当性を告発し、朝鮮学校関係者に寄り添い続けた記者たちの軌跡は、まさに「無償化闘争」の一部だ。
無償化裁判が終結した今日も、日本各地には子どもたちの学ぶ権利のために、必死に声を上げ続けている同胞たちがいる。
2025年に入り、大阪での「火曜日行動」が600回目を迎えた。東京中高の生徒代表、愛知と大阪の要請団が文科省への要請を行い、無償化適用を求める集会が大阪と東京で開かれた。
そして今年の4月、「朝鮮学校の公的助成の実現を目指す国会議員の会」が設立され、東京中高、朝鮮大学校を視察し、文科省に対する要請活動も行った。
これからも、在日同胞と日本市民らの共感と連帯の輪を広げ、勝利への強い信念を抱かせることこそが、「朝鮮新報」に託された役目である。
記者たちの「無償化闘争」は勝利のその日まで続く。
(尹佳蓮)




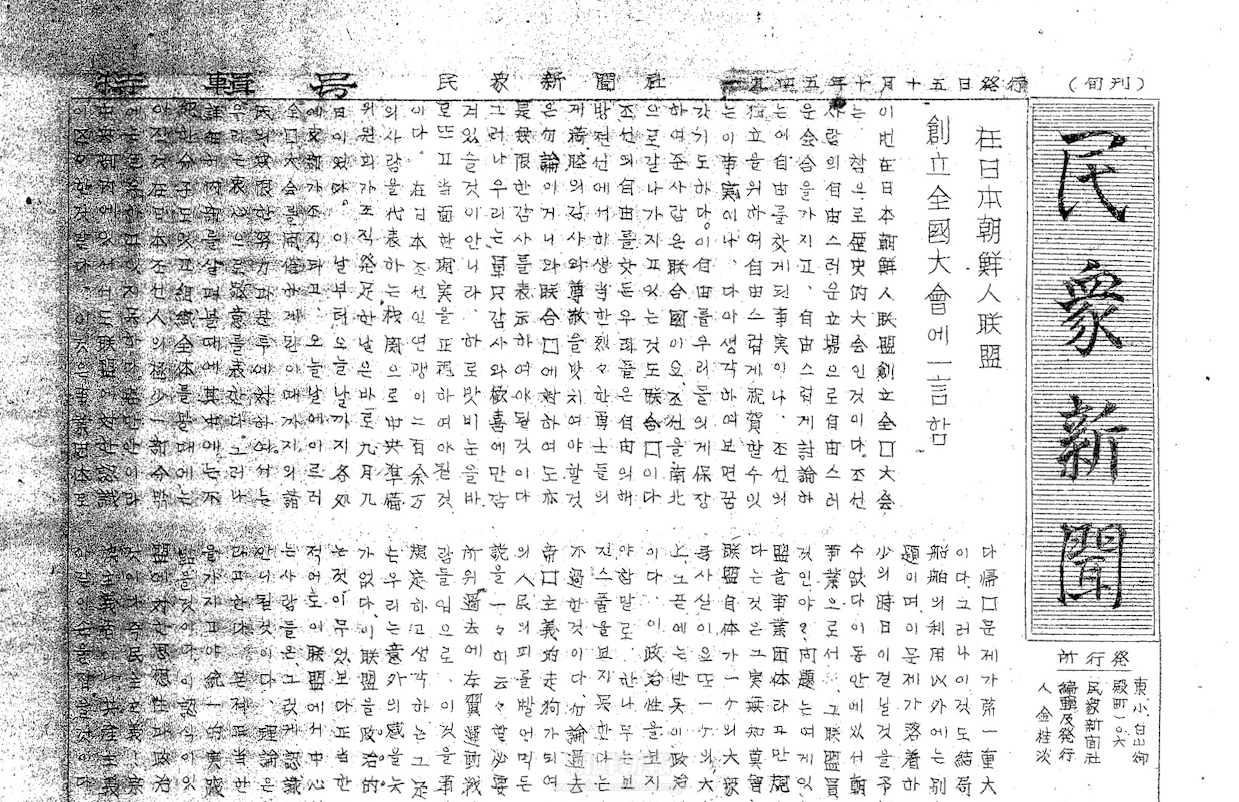 〈記者らが記した歴史の瞬間①〉結束と闘いの証/創刊から強制停刊、復刊へ
〈記者らが記した歴史の瞬間①〉結束と闘いの証/創刊から強制停刊、復刊へ  〈記者らが記した歴史の瞬間②〉待ち望んだ再出発の道/歓喜の渦、帰国の港で
〈記者らが記した歴史の瞬間②〉待ち望んだ再出発の道/歓喜の渦、帰国の港で 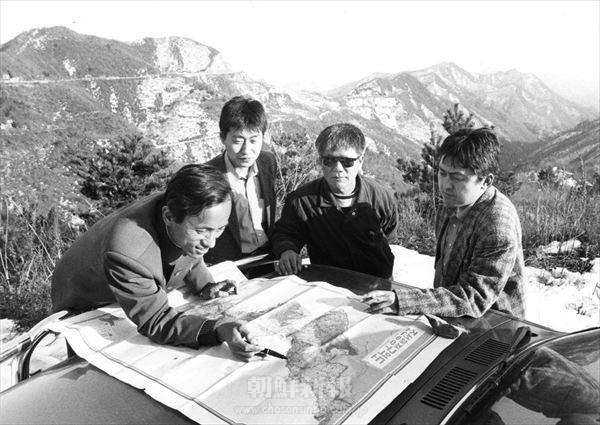 〈記者らが記した歴史の瞬間③〉苦難の日々、途絶えさせなかった声/朝鮮各地で現地取材
〈記者らが記した歴史の瞬間③〉苦難の日々、途絶えさせなかった声/朝鮮各地で現地取材  〈記者らが記した歴史の瞬間④〉同胞メディアの役目果たす/震災の現場で
〈記者らが記した歴史の瞬間④〉同胞メディアの役目果たす/震災の現場で  〈記者らが記した歴史の瞬間⑤〉念願の「全国」、記した道のり/インターハイ出場権の獲得
〈記者らが記した歴史の瞬間⑤〉念願の「全国」、記した道のり/インターハイ出場権の獲得