〈続・歴史×状況×言葉・朝鮮植民地支配と日本文学 73〉萩原朔太郎
2025年01月17日 06:00 寄稿植民地戦争経験の蓄積と「惨虐」
2024年は日清戦争から130年にあたる年だった。近代日本がはじめて経験したこの対外戦争は、発端は甲午農民戦争であり、その制圧を名目として朝鮮への本格的出兵をはたし、朝鮮半島を主戦場としてその支配権を争った戦争だった。朝鮮、さらに中国大陸へと利権拡大を進めたこの帝国主義的侵略戦争は、抗日抵抗する朝鮮の農民軍に対し「悉く殺戮すべし」の命令の下、3万から5万人が殺されたとされる、まぎれもないジェノサイドをともなう植民地戦争にほかならなかった。
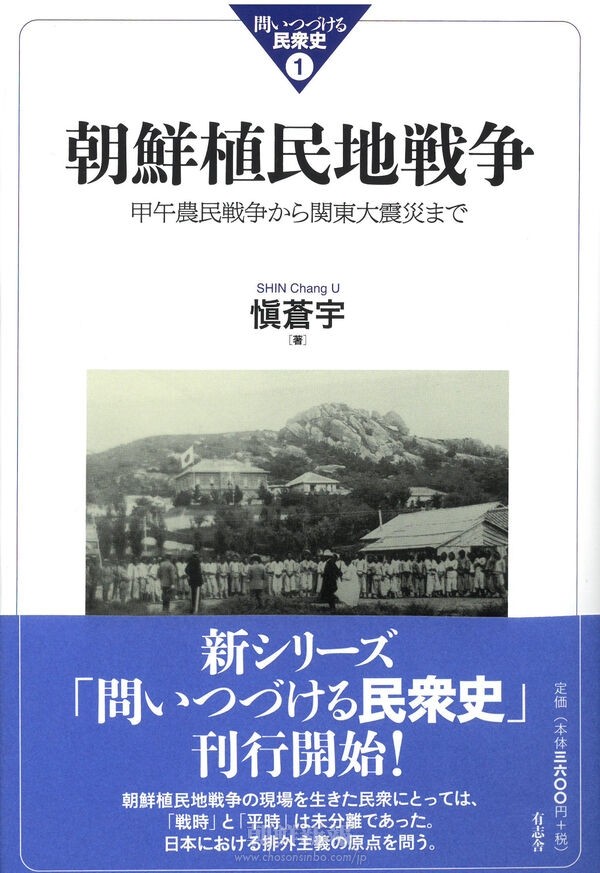
慎蒼宇著『問いつづける民衆史① 朝鮮植民地戦争―甲午農民戦争から関東大震災まで』(有志舎、2024年7月刊
昨年7月有志舎より刊行されたシリーズ『問いつづける民衆史』(全11巻)の第1回配本として上梓された、慎蒼宇・法政大学教授による著書『朝鮮植民地戦争―甲午農民戦争から関東大震災まで』は、このことを詳細に描いているが、同書の裏表紙に書かれた著者の執筆意図をそのまま紹介する。
「朝鮮の人びとは甲午農民戦争以降、50年以上にわたって日本の侵略と植民地戦争にさらされ続けた。それは彼我の力が圧倒的に違う『非対称戦争』であるがゆえに凄惨なジェノサイドを伴い、その延長線上に関東大震災時の朝鮮人虐殺は起こったのである。平等のない植民地戦争のなかで虐殺体験や朝鮮民衆への憎悪・恐怖を内面化した日本軍人・兵士たちと、その暴力にさらされながらも抵抗し続けた朝鮮民衆の姿を通して、植民地近代論のように、抵抗の領域を歴史の表舞台から周辺化しようとする傾向を批判し、日本近代史に圧倒的に不在だった植民地戦争の実態を描き出す」
近代以降日本が朝鮮およびアジアで引き起こした戦争や軍事行動、虐殺やそれらへの抵抗を、個別断片的な事象としてのみ捉え、かつ支配者側の視点で正当化、矮小化、断片化、隠蔽しがちな蒙をはらい、明確に「植民地戦争」と名指し、130年以上におよび現在まで連続する時間意識とともに一貫して捉える歴史認識へと導いてくれる力作である。来月、朝鮮大学校朝鮮問題研究センターでも著者を招いて書評研究会を開催する予定である。
さて、朝鮮植民地戦争経験の蓄積を、関東大震災朝鮮人虐殺の背景として指摘し研究し続けてきた著者と同書に強くインスパイアされながら、萩原朔太郎の二つのテクストを重ね読んでみよう。
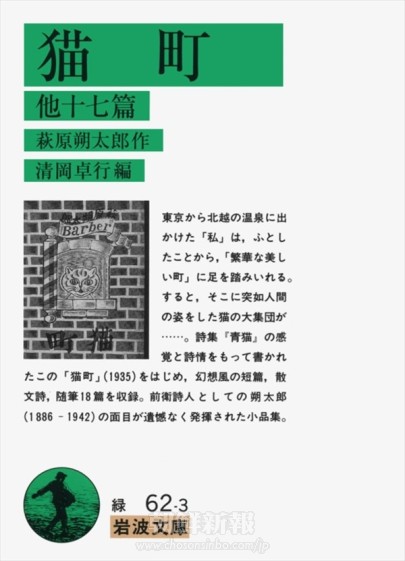
萩原朔太郎『猫町 他十七篇』(岩波文庫)。「日清戦争異聞(原田重吉の夢)」を収録
大震災当時、朝鮮人虐殺に際し「朝鮮人あまた殺され/その血百里の間に連なれり/われ怒りて視る、何の惨虐ぞ」(「近日書簡」[『現代』1924年2月])と日本人への怒りを書き残した「日本近代詩の父」萩原朔太郎は、他方で数少ない小説を残しており、その中に「日清戦争異聞(原田重吉の夢)」(「生理 終刊第5号」1935年2月)という小編がある。
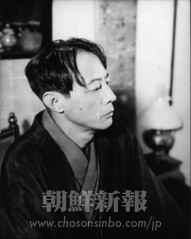
萩原朔太郎(1886-1942)
この作品は、日清戦争時、平壌を占領した際、決死隊として一番乗りで軍功をたて英雄となり金鵄(きんし)勲章を授与された原田重吉の生涯を虚実まじえて描いたものだ。原田は凱旋帰国後、祝福の嵐に酔い、放蕩の末、自らを主人公とする壮士芝居に出演し、戦地での自分の役を演じる。辮髪(べんぱつ)の「支那兵」30人をなぎ倒した自らの武勇伝をいっそう誇張的に演じながら巡回公演し、原田はますます有名な国民的英雄となった。だがやがて博打で生活はすさみ勲章まで剥奪された原田は零落し、ついに「ルンペン」にまで身を持ち崩す。浅草公園のベンチで「支那兵」との博打を夢に見たかれは、目覚めても自分の日清戦争の手柄がなんだったかももはや思い出せない。「そんな昔のことなんか、どうだって好いや!」と口走り、再び眠って二度と目覚めない原田の姿は、かつて戦地で見た哀れでみすぼらしい「日傭人の支那傭兵」とそっくりだった…。
実在の原田重吉は借金返済目的で芝居に出演し、その後は日露戦争にも召集され、以後1938年に死去するまで郷里で農業に従事し続けたのだったが、日清戦争の舞台が朝鮮であったこととともに、「支那兵」への差別的言動にまみれたこの「国民的英雄」の虚構性(それも派手に誇張された軍国美談を自ら演じ、さらにその末路を「野蛮」とみなした中国人と重ねる、という二重三重の)をこのように描いた朔太郎の想像力に、強烈な印象を受けずにはいられない。1935年という、大陸侵略戦争が本格化していった当時において、さらに関東大震災時朝鮮人への「惨虐」へ示した「怒り」と重ね読めば、そのような日本人民衆に滲透しきった差別観と残虐性、それを着々と蓄積し続けた植民地戦争の経験が、二つのテクストを結ぶ朔太郎の歴史意識となって、そして「そんな昔のことなんか、どうだって好いや!」という、健忘症的現代日本への警句となって、浮かびあがってくるだろう。
(李英哲・朝鮮大学校外国語学部教授)



