〈読書エッセー〉晴講雨読・恩師の著書『現代物理学の世界』と『理系の言葉』(上)/任正爀
2025年11月19日 09:14 寄稿今年10月、筆者は古希を迎えた。
あまり実感はないが、それでも年を重ねた分だけいろんな事があった。とくに、水晶のような美しい物を得たような素晴らしい出来事とともに、転機といえることが二つある。一つは中学からウリハッキョに通い朝鮮人としての自覚と誇りを持てたこと、もう一つは大学院を修了し、朝鮮大学校で教育および研究活動に専念できたことである。
今回はそんな大学院時代の恩師二人の著書、久保謙一『現代物理学の世界』と土岐博『理系の言葉』を取りあげたい。
朝鮮大学校卒業生の大学院受験を公立で初めて認めたのが都立大で、1976年のことである。同じ年に私立の上智大、東海大も認め、その約20年後に国立である京大も認めて今日に至っている。筆者が都立大大学院に入ったのは1978年で、その時の指導教官がドイツから戻ってこられたばかりの久保謙一先生である。
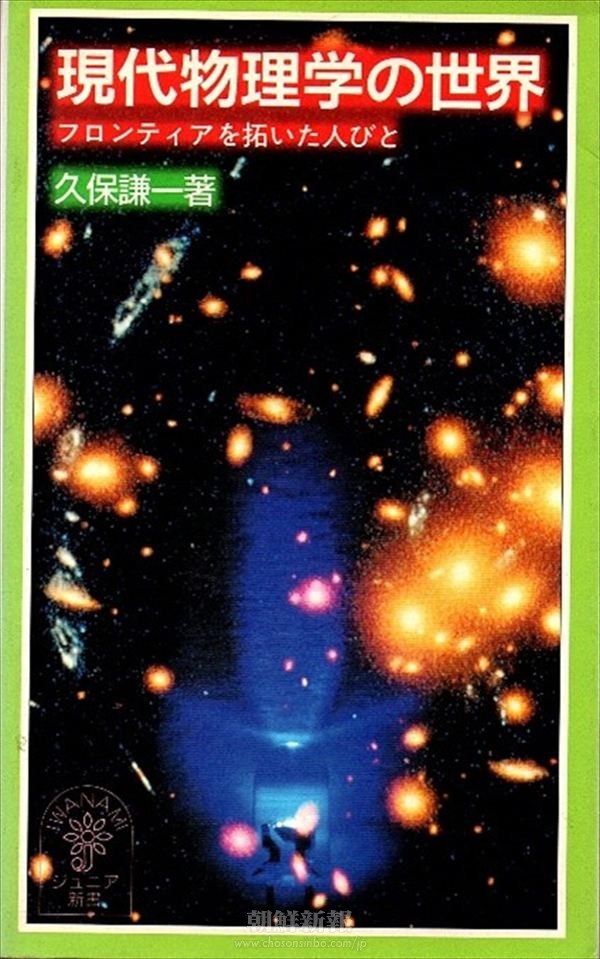
『現代物理学の世界』
1998年に岩波ジュニアブックスの一冊として出版された『現代物理学の世界』は、「光は湾曲したか」「ニュートリノを予言した人」「中性子星にまつわる光と陰」「青色ダイオードに賭けた人」「新元素合成と1つの表の重み」の5章から構成されている。
本の表紙には「微小な素粒子の研究から、広大な宇宙の謎の探究まで、今日、物理学の躍進は一段とめざましい。本書は、ニュートリノを予言したパウリ、パルサーを発見したベル、青色ダイオード開発の中村修二など、20世紀の最先端を切り拓いた人々の業績を、人間味あふれるエピソードで紹介、読んで面白い物理の世界に読者を誘う」とある。多岐にわたる現代物理学のなかでも5つの話題に特化しているが、現代物理学の一断面を人間ドラマとして描こうとしたことが最大の特徴である。なかでもとくに興味深いのは「中性子星」を発見したジョスリン・ベルの逸話である。
1967年、ケンブリッジ大学の電波天文学者A・ヒューイッシュ教授の学生であったジョスリン・ベルは宇宙からやってくる電波の観測記録を調べていて、そのなかに強弱の規則性がある信号を発見した。当時、この発見をめぐって宇宙人からの信号ではないかという議論もあったそうだが、ベル女史は複数の異なった位置からの信号を確認し、それはあり得ないことを示した。
その後、その正体は中性子星の回転による規則的電気信号であることが明らかになる。中性子星はいわば中性子だけから作られた巨大原子核で、パルス状の信号を発信するので「パルサー」と呼ばれる。
パルサーの発見は電波天文学の輝かしい成果であり、1974年にノーベル賞が贈られたが、授与したのはヒューイッシュ教授であった。多くの人が疑義を唱え、ある人がベル女史にノーベル賞を受賞してもよかったのではと質問すると、次のように答えたという。
①指導する先生と学生の間の境目の論争はいつも難題で、解決することはないでしょう。②研究プロジェクトの成功、失敗の最終責任は指導者が負うものです。指導者が学生の失敗をとがめるケースはよく耳にしますが、大半は指導者の落度です。一方指導者は成功の恩恵をこうむることがあってもよいと思います。③まだ研究者の卵である学生が受賞するとなると、ノーベル賞の価値が落ちることになると思います。もっとも、非常に例外的な場合はあると思いますが、私の場合がそれだとは考えません。④結局、私が決めることではありません。私はいい同僚であると思っています。
この時、ベル女史は31歳であったが、見事な見解である。ノーベル賞はなかったが、その後も優れた研究成果をあげて、たくさんの受賞歴がある。実は筆者はベル女史をすっかり過去の人と思っていたのだが、思わぬところでその名前を見た。2006年8月の国際天文学連合総会で、それまで太陽系の惑星であった冥王星が外されたが、この時の総会議長こそベル女史であった。
著者は原子核物理の専門家であり「新元素合成と一つの表の重み」も興味深いものがあった。自然界に存在しない原子核を実験的に生成しようとする試みと、その過程で発見された核分裂を主題に置いている。副題に「原子核物理、今世紀を経て21世紀への科学者と市民」とあるように、それが原子爆弾と原発に至る過程を分析し、どのような教訓が得られるのかを考察している。
久保先生は温厚な人柄であったがいわば完璧主義で、本書もジュニア向けではあるが安直な説明で終わらず精査した内容となっている。
筆者が大学院と関連して今でもはっきりと覚えているのは入試である。一次の筆記試験をなんとかかクリアーして、二次の面接試験に臨んだが、筆者の前にはボーア、モッテルソン『原子核の構造』という洋書が置かれていた。後で知ったことだが、この分野では古典的名著といわれるものである。設問はそのなかの公式を説明せよというものであったが、ほとんど何も答えられなかった。「これでは無理かな」という久保先生の言葉に「何とか頑張ります」というのが精いっぱいであった。その時、助け船を出してくださったのが、後に『質量の起源』(講談社・ブルーバックス)をはじめ数多くの解説書を出される広瀬立成先生である。当時は、素粒子実験研究室の助教授で、「久保先生は優しい人だから、もし院に入ったならしっかりと学びなさい」と激励してくださった。合格発表は掲示板で行われたが、初めての経験であり本当に緊張した。
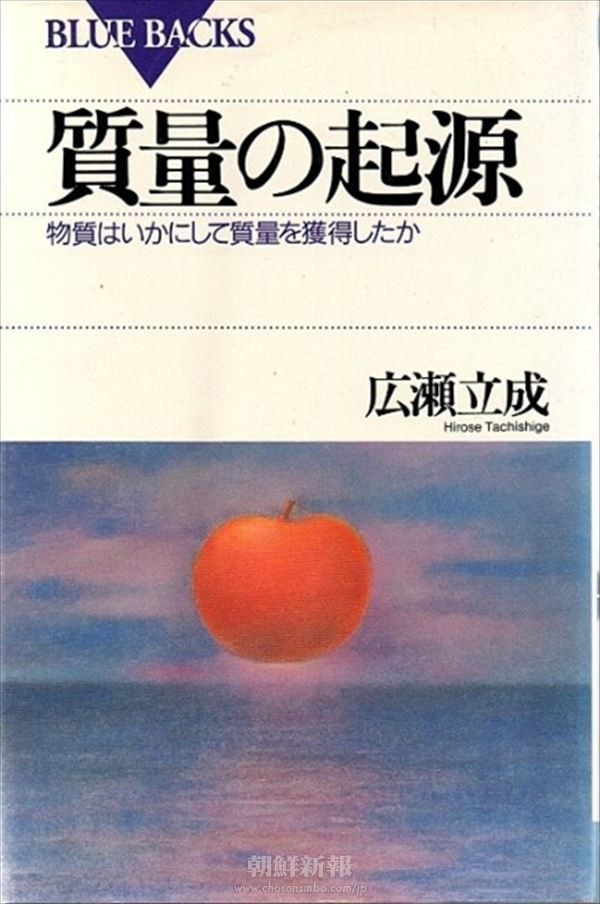
『質量の起源』
何とか大学院に入ることができたが、当初は同期に後に信州大教授となるY君がいたので、朝大卒という変わり種をとってくれたのかと思っていた。ところが、そうではなく久保先生は朝鮮問題にも関心が深く、東大助手の時には朝大認可の署名運動にも積極的に参加されたという。人生には運がつきものだが、立派な先生方と巡り会えて本当に運が良かったとつくづく思う。
(朝大理工学部講師)



