〈読書エッセー〉晴講雨読・朝鮮の文化・歴史をテーマとした大衆小説/任正爀
2025年07月16日 08:09 寄稿読書が趣味という人は多い。筆者もその一人であるが、もっともそれを基に本紙に「晴講雨読」を書いたりするのだから、半分は仕事のようなものである。ちなみに、今回で51回目となり、これまで取りあげた本は100冊ほどになる。
さて、読書のなかでも、多くの人は小説を念頭に置いているのではないだろうか。純文学をはじめ歴史小説や推理小説など、そのジャンルと扱うテーマは実に多種多様であるが、残念ながら日本では朝鮮に関するものはあまり多くはない。ここでは、その少ない中から筆者が興味深く読んだ朝鮮の文化・歴史を描いた大衆小説を紹介したい。
まずは、1985年に文芸春秋から出版された赤瀬川隼『潮もかなひぬ』である。題名は万葉集の額田王(ぬかたのおおきみ)の詠んだ歌の一句で、小説はその歌を含めた万葉集の解釈がテーマとなっている。
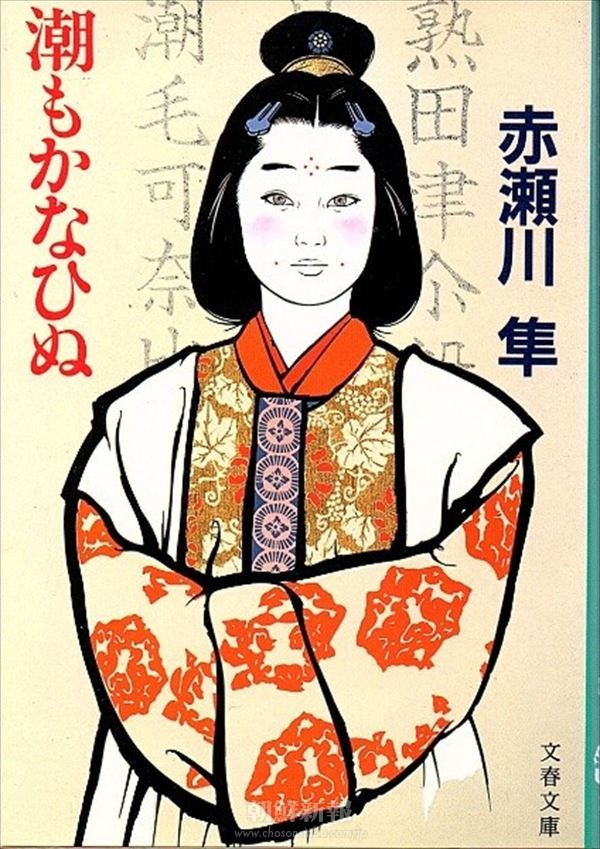
『潮もかなひぬ』(文庫本)
物語は主人公であるルポライターが、後輩の女性から祖父の死についての調査を依頼されるところから始まる。
エリート商社マンであった祖父は、戦時中に特高警察に連行され、その時の拷問がもとで死に至る。ところが、残された家族は、政治的に無色であった祖父がなぜ特高に連行される羽目になったのか見当がつかない。ただ、祖父は万葉集の研究が趣味であり、死ぬ間際にも「人麻呂と心中」という言葉を残したという。
日本に現存する最古の和歌集である万葉集と治安維持法、そこに朝鮮がどのように絡み合うのか。また、柿本人麻呂は謎の人物で、小説ではその実像にも迫る。ちょっとネタばれになってしまうが、万葉集を古代朝鮮語で読み解くことがキーポイントになっている。
元は第90回直木賞候補作にもなった短編で、審査者の一人井上ひさしは「今回の題材は、この枚数で支えるには巨きすぎたかもしれない。そこで作者の美点がそれぞれ幾分かずつ損われてしまったのではないか。とにかくこれは凄い題材ではある」と評した。そこで、その短編を読んでみたが、大幅に加筆された単行本はストーリーも洗練され断然面白いものとなっている。その後、文庫本も出版された。本稿を書くにあたり読み直してみたが、以前と同じような満足感とともに、著者の朝鮮文化への敬意と日本の植民地政策への批判を確認することができた。
同じく万葉の時代を背景としたものに『北風に立つ-継体戦争と蘇我の稲目』(中央文庫)、『聖徳太子-日と影の王子』(文春文庫)、『落日の王子-蘇我入鹿』(文春文庫)など黒岩重吾の一連の歴史小説がある。黒岩重吾は松本清張に次ぐ社会派推理小説作家として知られているが、古代史をテーマとした小説も多い。とくに、ここで挙げたものは、稲目にはじまり馬子、蝦夷、そして入鹿に至る飛鳥時代の権力者・蘇我氏の興亡を描いたものである。
作者は、蘇我氏を百済王の血族である渡来氏族とし、彼らが日本古来の神道の祭司権を持つ氏族と対抗するために仏教を取り入れ、その権威によって自己の権力を確立・維持しようする姿を興味深く描いている。背景にある朝鮮三国の政治情勢と倭国の関係が重要な伏線となっており、当時の朝・日関係の状況を知るうえでも興味ある小説である。
次に紹介するのは、1991年に新潮社から出版された宮本徳蔵『虎砲記』である。
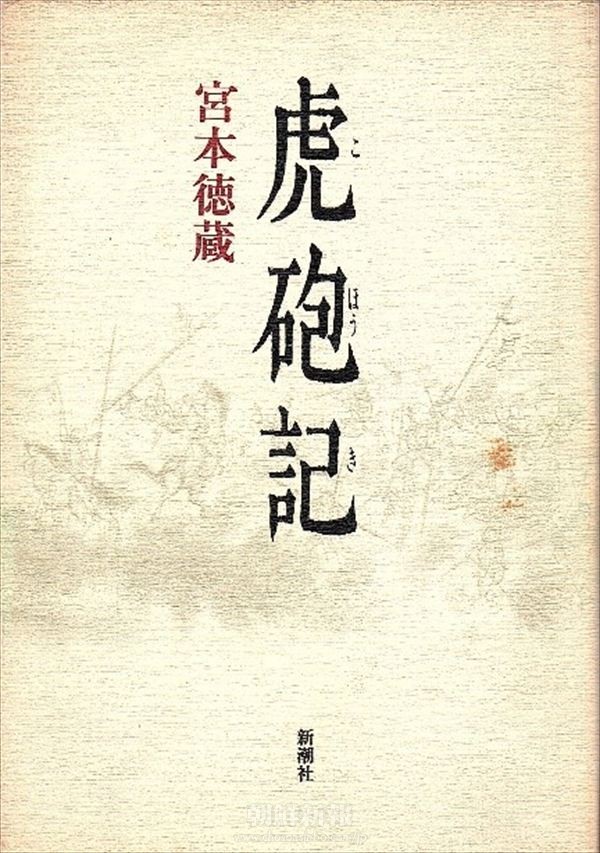
『虎砲記』
時代背景は壬辰倭乱で、主人公は加藤清正の家臣・岡本冴香である。冴香は22歳の若さでありながら老成し、体も小さくとても剛の者には見えない。戦場でも戦を放り出して、日本軍が占拠した城で、まるで火事場泥棒のように朝鮮の本を収集する人物で周りの評判も良いはずがない。その彼が、加藤清正が虎と対峙した時、見事な砲術で主君の命を助けるのだが、かえって主君に恥をかかせたとして、謹慎処分に処せられる。かねてより朝鮮への憧れを抱いていた冴香は、郎党を引き連れて朝鮮側に身を投じる。冴香の砲術を高く評価した朝鮮側は一軍の将として迎える。彼は大きな功を挙げて、金忠善という朝鮮名を与えられ両班に遇せられる。
金忠善は、『朝鮮王朝実録』『承政院日記』などに金沙也加という名前で記されている実在の人物で、彼の子孫が今も慶尚北道達城郡の友鹿洞に住んでいる。金忠善は慕夏堂の号で知られ、子孫によって編集刊行された『慕夏堂文集』には、彼の伝記と年譜の類が収められている。
ただし、その信憑性が問題視されたが、中村栄孝『日鮮関係史の研究』で詳細に検討されて以来、金忠善の存在とともに『慕夏堂文集』は確かなものとして研究者には受け入れられるようになった。
宮本徳蔵は在日朝鮮人として生まれたが、日本人の養子となったという。仏文学を専攻し40歳を過ぎて作家としてデビューした。どのようにして金忠善の存在を知ったのかはわからないが、自身と対照的な人物として彼に興味を持ったのかもしれない。
『虎砲記』は柴田錬三郎賞を受賞したが、金忠善が多くの人に知られるようになったのは、NHKの番組「歴史発見」によってである。題名にある通り歴史の影に隠れた真実を再発見するというもので、そこでは豊臣秀吉による朝鮮侵略の敗退の主因は、朝鮮側に投降した多数の日本人武将(彼らは降倭と呼ばれた)と彼らによってもたらされた火縄銃の威力によるというもので、その代表人物として金忠善が紹介されていた。金沙也加は戦国時代に活躍した鉄砲集団雑賀衆の一人で、その「沙也加」(さやか)という呼び名も、「雑賀」(さいか)から付けられとする。ただし、降倭と彼らによる鉄砲技術によって朝鮮が勝利を得たとするのは本末転倒だろう。
日本では、小説を含めて朝鮮関係の本は少ない。その根本要因は植民地過去清算問題が未解決であり、朝鮮への差別意識が残っているからだろう。卵が先か、鶏が先かではないが、そのような状況を変えるためにも朝鮮関係のより多くの本が出版されることに期待したい。
(朝大理工学部講師)



