〈続・歴史×状況×言葉・朝鮮植民地支配と日本文学 74〉花田清輝
2025年02月15日 06:00 寄稿知的抵抗としての反語的精神
「集団は個人を圧迫するでもあろう。しかし、集団が、集団内部の矛盾を、一つ一つ解決していく過程において、はじめて個人の主体性は確立されていくのではなかろうか。いかにも個人は集団のなかにあって単純化されるでもあろう。だが、その単純化のなかに無限のゆたかさがあるのは、個人が、個人として切り離されているばあいには、ほとんど気づかない――気づくことにさえためらっている、みずからの正体が、集中的に表現されているからだ」。作家・評論家の花田清輝が、1974年に書いた「金いろの雲」という評論の一節である。集団・組織と個人、政治と文学芸術との関係をダイナミックにとらえ、個人化、脱政治化と葛藤しながら営む私たちの組織と運動、民族教育が標榜する集団主義の生きた内実をとらえる言葉として、筆者は大切にしている。さらには社会主義社会とそこに生きる人民大衆について、個人はただただ抑圧され、自由が制限され、もっぱら画一的で全体主義的だと嘲笑して悦に入っている俗流反共言説への、痛烈な批判にもなろう。
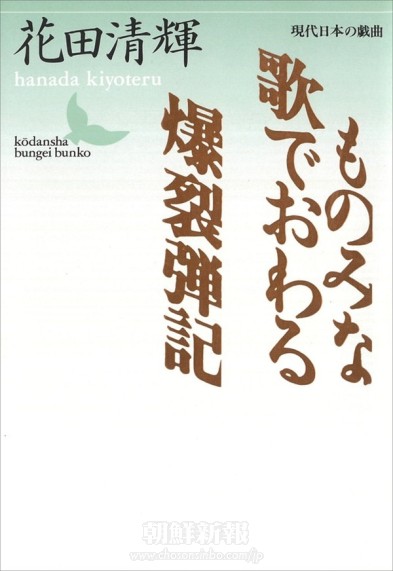
『ものみな歌でおわる・爆裂弾記』(講談社文芸文庫)
花田自身、戦後日本においてさまざまな文学者の会、芸術家集団の組織者、編集者として、芸術の総合化すなわち大衆化を、通俗化とは逆に破壊と創造の批評精神に満ちた主軸に置き、共同制作・集団制作としての芸術運動を生涯のテーマ、実践として取り組み続けた。常に歴史を抽象的にではなく具体的な「形」が新たに変転していく「転形期」ととらえ、「前近代を否定的媒介にして近代を超える」、二つの焦点をもつ「楕円」の思想、対立物を対立したまま統一する特異な弁証法といった、独自の思想と論理を、古今東西の文学、芸術、政治、社会に関する博覧強記と豊穣なレトリックを華麗に駆使し、既存の形式論理や二項対立を解体しつつ現実に介入していった花田の仕事は、硬直した対立と、敵を単純化する暴力的な言葉に満ちた現代世界において、今こそ再読されてしかるべきだと思う。
花田は日本の共産主義運動やプロレタリア文学が弾圧され総崩れとなった1930年代半ばに、これらの運動とほとんど無関係の地点で、独力でマルクス主義者として自己形成し独り抵抗を実践していった。それも右翼団体の機関誌『東大陸』の編集に関わりながら。花田はこれを逆用し大胆不敵かつしたたかに帝国主義批判を展開する。朝鮮人ジャーナリスト李東華の秘書となり、1935年に「満州」の朝鮮人居住区を視察した後、花田は論文「朝鮮民族の史的変遷」「民族問題の理想と現実―『内鮮一体化』問題を中心に」などで、朝鮮・台湾への植民地支配や中国への侵略を正当化し美化する帝国主義イデオロギーに対して、そのような「理想」は到底現実化されていないと、反語的偽装文体で辛辣に皮肉り、批判していた。
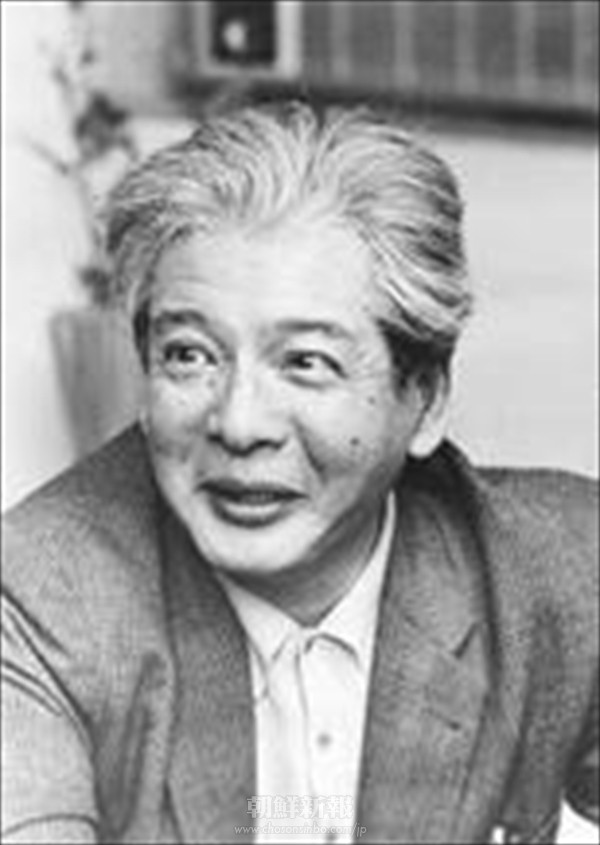
花田清輝(1909‐1974)
苛烈な思想統制・言論弾圧の中でもこうした知的抵抗戦術で朝鮮支配についての批判的認識を蓄積していった花田は、戦後にも、たとえば1959年の評論「ノーチラス号応答あり」で、当時の「皇室ブーム」の中、天皇の「ご真影」を日本人に押し売りする、知り合いの朝鮮人のことを紹介している。恭しく額入りの写真を取り出せば日本人はついつい平伏して買わずにはいられなくなる。曰く、「日本人の弱点をたくみにつかんだ押売りの方法を、いかにも天皇制にさんざん痛めつけられてきた朝鮮人らしいおもいつきだと考えて感心した。毒をもって、毒を制す、とはこのことである」。天皇制を内面化させられ自己否定の「マゾヒズム」に苦しめられてきた朝鮮人が、しかしこれを逆に日本人に向かってそっくり投げ返すしたたかさで、「マゾヒズムを、あざやかにサディズムに転化することができたのだ」と花田は痛快に評している。
1962年作、63年初演のち68年「明治百年批判公演」として再演の風刺喜劇「爆裂弾記」は、1885(明治18)年、自由民権運動を背景に、やがて民権論者が国権論者へと転じ、征韓論のあおりとともに、朝鮮に乗り込み閔妃(明成皇后)や清国を撃つべしと息巻く愛国壮士たちと、言論の自由と非戦論を堅持する新聞社との緊張感のなか、爆弾テロを企む壮士たちの過激な運動が壊滅していく顛末を描いた。ナショナリズムを暴走させる奔放無謀なエネルギーとその挫折を否定的媒介とし、60年安保闘争、韓日条約など同時代の激動のなか若い世代に向けて、異なる未来への突破口となるべく花田は願ったようだ。依然支配権力へ自発的に従属するマゾヒズムから一歩も自由たりえず、朝鮮、中国を「膺懲」すべしなどと息巻く今日の日本人にとっても、辛辣痛烈な反語的作品であろう。
(李英哲・朝鮮大学校外国語学部教授)



