〈読書エッセー〉晴講雨読・本とは何かを問う小説『華氏451度』/任正爀
2024年12月25日 09:00 寄稿本紙に『晴講雨読』を連載して3年以上が過ぎた。本来は晴れた日に畑を耕す「晴耕」であるが、筆者のおもな仕事は大学での「講義」なので、それをもじって晴講雨読という訳である。また、「読書エッセー」は編集者が付けたもので、それによって気を楽にして書くことができ助かっている。
「広く、深く」を目指しながら様々な本を紹介してきたが、当初よりいつかは取りあげなければと思っていた本がある。それがレイ・ブラッドベリ『華氏451度』である。というのも、この小説は本とは何かを問う問題作だからである。普段用いる摂氏では223度で、華氏451度とは紙が燃える温度である。ちなみに、米国のマイケル・ムーア監督によるドキュメンタリー映画『華氏911』の題名はこの小説に倣ったもので、「それは自由が燃える温度」というキャッチフレーズがつけられていた。
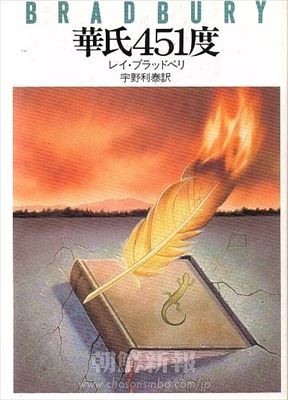
『華氏451度』(旧訳版)
小説は近未来を舞台としたもので、為政者は一般大衆を統治するために本を禁止する。それは人々が本を通じていろんな知識を得るとともに、様々な感情に揺り動かされるという理由による。そして、本が見つかると燃やすのだが、それを行うのは「ファイヤーマン」と呼ばれる人たちで、その社会でエリートとされている。
主人公はこのファイヤーマンなのだが、ある時、通報があって出動すると、本を所持していた老婆は退去を拒み、本と共に焼け死んでしまう。本とは自身の命を犠牲にするほどのものなのかと主人公は衝撃を受け、自分の任務に疑問を抱く。そして、本を隠し持ち、それに反対するレジスタンスとなる。
この小説の内容を知ったのは、高校生の頃にテレビで放映された映画によってである。映画の最後で主人公はレジスタンスの村にたどり着くのだが、その村の住人はみな小説を丸ごと一冊暗記していて希望者にそれを語る。映画では、語り部の住人たちが紹介されるのだが、かれらを、あの人は『戦争と平和』、あの人は『罪と罰』というふうに書籍名で紹介するのである。
変わった映画だなというのが当時の感想で、敢えて原作を読もうとは思わなかった。それが数十年の時を経て、筆者の前にクローズアップされたのは、日本経済新聞・日曜版の「名作コンシェルジュ」によってで、「書物が禁じられた世界/強烈な批判潜ませ描く」という見出しで内容を紹介していた。懐かしさもあって改めて本を手にしたのだが、その結末は映画以上に深刻、かつ哲学的であった。
余談であるが、普段、日経はほとんど読まないのだが、日曜日の夕方いつも行く銭湯に置いてあり、風呂あがりにそれに目を通す。ちなみに、この銭湯には無料のスチームサウナがあり、そのなかで原稿の構想を練る。ゆえに、本紙の多くの記事はここで生まれたものである。
原書の出版は1953年であるが、日本では3回翻訳本が出版されている。一番新しいものは2014年に新訳として、ハヤカワ文庫の一冊として出版されたものであるが、訳者は英文のダブルミーニングに留意すべきと強調する。扉の頁に「もし連中が罫線用紙をよこしたら、逆向きに書きなさい」という文章が掲げられているのだが、まさにそれがダブルミーニングで、その意味するところは「もし連中がルールを押しつけてきたら、反逆しなさい」で本書のテーマとなっている。
もう一つ、この文章が重要と思われるのが、ファイヤーマンの隊長に関するものである。主人公が老婆を焼死させたことを悔やんで欠勤していることを知って、隊長が会いにくる。そして、彼を説き伏せようと本の弊害を語るのだが、それは逆にこの隊長がいかにたくさんの本を読んでいるのかを示す。同時に、その反対の意味で本の素晴らしさを説くものとも受け取れる。
この本が書かれたのは米国で「赤狩りの嵐」が荒れ狂った時で、旧訳版の解説では次のように書いている。
「彼(ブラッドベリ)はSF作家であった。現実のマッカーシズムをその現象面で捉えることは、彼の仕事ではなかった。かれはむしろ、マッカーシズムが多くのごく一般的な市民たちを何の造作もなく巻き込み、呑みこんでいく有様に、より普遍的な問題を見出した。市民たちが、おのずから思想統制とおなじ画一的な考え方に馴染んでいく姿は、人間の持っている非知性的なものへの根強い衝動を、彼にイメージさせた。彼は、そうした衝動から、守り抜くべきものは何かと考えた。それは彼にとって、あまりに自明な問いだった。精神の自由と、個人の尊厳と―そしてその証拠としての活字文化だったのである。」
ある人は「文明とは知識で、文化とは知恵である」と言ったらしいが、『華氏451度』の世界とは逆に今は本が氾濫している。その中から文化としての本を見極め、自身の糧とする。本書を読んで改めて思ったことである。
作者であるレイ・ブラッドベリはSF小説の大家として知られているが、その代表作は『火星年代記』である。地球人がロケットで火星を探検し移住するというストーリーなのだが、火星にはすでに住人がいて、彼らとの不思議な物語を26の短篇で綴っている。
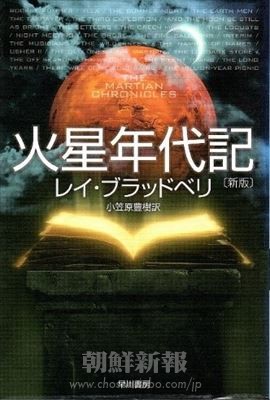
『火星年代記』
ブラックユーモアに溢れ、時に鋭い人間批判も見られる。読みながら、この物語はどのように終わるのか気になったのだが、こちらもちょっと哲学的である。テイストが星新一のショートショートに似ていると思っていたら、星新一はまさにこの本を読んで作家を志したそうだ。
さて、最後に『華氏451度』と関連するエピソードを紹介しよう。今から数十年前、子どもたちと変身型ロボットのテレビアニメを見ていた時のことである。敵のロボットが図書館を襲おうとしていた時、主人公の少年が図書館に入り、本を探す。そして、「あった!」と見つけたのが『華氏451度』だった。少年は本が燃える温度を確認しようとしていたのである。思わずうなってしまったが、子どもたちはむろんその本を知らない人が見たら、何のことかまったくわからない。おそらく、スタッフの中にその小説に強い思い入れをもった人がいたのだろう。少年のキャラクター(名前はケンジ君だったような気がする)はなんとなく憶えているので、そのアニメの題名を知りたくてネットで調べてみたのだが見つからない。というわけでこの話は筆者のなかの都市伝説となっている。
(朝大理工学部講師)



