〈読書エッセー〉晴講雨読・内田樹の「街場」シリーズを読む/任正爀
2024年11月20日 08:00 寄稿前回「独自の哲学を愉しむ」という表題で内田樹先生の『ためらいの倫理学』と『「おじさん的」思考』を紹介したが、その後もブックオフの文庫本廉価コーナーで先生の本を購入し読み続けている。このコーナー、以前は100円均一だったのだが、最近は200円も混じる。安いから古本を買う筆者にしてみれば、わずかであるがその差が気になる。内田先生の本も100円のものしか購入しないが、そのうちの一冊が『街場のマンガ論』である。
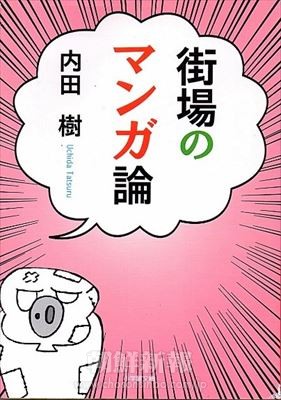
『街場のマンガ論』(文庫本)
「街場」というと筆者は、居酒屋で一杯呑みながら様々な話題で盛りあがる場面をイメージする。内田先生の著書には『街場の〇〇論』という題名が多いが、そのシリーズはまさにいろんな所に書いたものを集めたもので、よく言えば多彩、悪く言えば雑多であるが、気楽に読めて新しい発見がある。
小学生の頃にテレビが普及し、鉄腕アトムや鉄人28号などのアニメに夢中になったが、筆者よりも5つ年上の内田先生はまさに戦後マンガのなかで育った人で、「これほど好きなジャンルは他にない」と語る。『街場のマンガ論』はそんな著者がマンガについて書いた文章を集めたもので、小学館から2010年に単行本が、13年に文庫本が出版された。
文庫本の裏表紙には「雑食系マンガ・リーダーの著者が世界に誇る日本マンガについて熱く語る!『エースをねらえ!』から〝男はいかに生きるべきか〟を学び、『バガボンド』で教育の本質を知る。手塚治虫の圧倒的な倫理的指南力に影響を受けた幼少時代、今なお、読み続ける少女マンガ…。日本でマンガ文化が突出して発展した理由を独自の視点で解読」とその内容を紹介している。
井上雅彦論、マンガと日本語、少女マンガ論、オタク論・ボーイズラブ論、宮崎駿論、マンガ断想、戦後マンガ家論の7章から構成されているが、マンガを通じての文化論、教育論、社会論は実に面白い。とくに第6章の「アメコミに見るアメリカのセルフイメージ」には感心した。そこでは、スーパーマンやバットマン、スパイーダーマンはアメリカの自画像以外の何物でもないとする。では、日本のセルフイメージは何か? それは鉄人28号に始まり、マジンガーZ、ガンダム、エヴァンゲリオンに繫がる操縦型ロボットであると指摘する。
「『鉄人』は米軍(および創設されたばかりの自衛隊)を表している。だとすれば、その操縦を委ねられている『戦後生まれで、侵略戦争に加担した経験を持たない無垢な正太郎少年』は、論理の経済からして、『憲法9条』の表象以外にはありえない。戦後マンガは『軍隊』(巨大な暴力装置)と『憲法9条』(イノセントな心)が『合体』するときだけ『よいこと』が起きるという物語を執拗に、ほとんど偏執的に繰り返してきた。つまり、戦後マンガは日米関係だけを集中的に描いてきたのである。マンガ家たちは、この定型的話型を通じて、国民の集合的無意識を表象し続けてきたのである」
たかがマンガ、されどマンガ、これは一例でその本によって改めてマンガの奥深さを認識したが、内田先生の洞察力にも脱帽である。
余談であるが、日本のマンガの第一者といえば手塚治虫である。ところが、サザエさんの作者である長谷川町子は国民栄誉賞を受賞しているが、手塚治虫は受賞していない。理由は明白で彼は共産党シンパで、社会性の強いマンガを描くからである。そのなかには「ながい窖(あな)」という朝鮮人を描いたものもある。
主人公は帰化して大企業の専務に収まる朝鮮人で、題名の「ながい窖」は解放前に強制労働させられた炭鉱の坑道のことである。朝鮮人であることを隠して生きてきたのだが、ある時、大村収容所から逃げてきた青年を匿うことになり、様々な出来事が起こる。1970年に書かれたもので、少し前にその存在を知りネットで読むことができたが、正直、ここまで朝鮮問題を詰め込むのかと驚いた。火の鳥、ブラックジャックをはじめ手塚マンガの面白さは言うまでもないが、彼の凄さを改めて知った。ちなみに『街場のマンガ論』表紙のイラストは、手塚マンガでお馴染みの「ヒョウタンツギ」である。
さて、最後になったが前回に続いて内田先生の本を取り上げた理由を述べよう。前回の記事が掲載された直後、友人から内田樹は天皇主義者を公言しているが、それについて指摘すべきではというメールをもらった。



