〈読書エッセー〉晴講雨読・司馬遼太郎の対照的な二つの小説/任正爀
2024年05月23日 09:40 寄稿去年は日本の国民的作家といわれる司馬遼太郎生誕100年であった。それを記念するイベントもあったはずだが、それほど話題となった感じがしない。近年、「明治の指導者、国民は良かった。戦前の昭和は本来の日本ではなかった」という「明治栄光論」を含む歴史観の問題点が指摘され、その功罪が問われていることと関係しているのかもしれない。
筆者はこれまで司馬遼太郎の小説は読んできたほうであるが、感銘を受けたものがある一方で、これはどうかなと思うこともあった。今回はそんな対照的な二つの小説『故郷忘れじがたく候』と『花神』を取りあげたい。
まずは、1976年に文春文庫として出版された『故郷忘れじがたく候』である。豊臣秀吉の朝鮮侵略、すなわち壬辰倭乱を日本では「焼き物戦争」ともいう。というのも、この時に大量の朝鮮陶磁器が略奪され、数多くの陶工たちが連れてこられたからである。一方的な侵略にもかかわらず、「焼き物戦争」というのはどうかと思うが、彼らによるものが唐津焼、高取焼、萩焼、薩摩焼、小鹿田焼である。
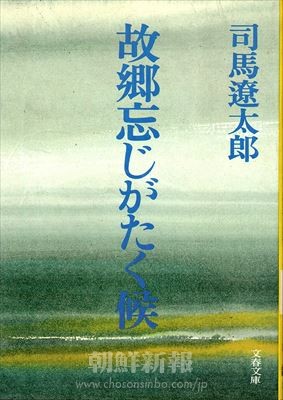
『故郷忘れじがたく候』
『故郷忘れじがたく候』の主人公は苗代川の薩摩焼陶工第14代沈寿官で、小説というよりもルポあるいは紀行文という性格のものである。薩摩焼の成り立ちと苗代川に住む人々の生活、とくに綿々と受け継がれてきた血脈の意味を自問する沈寿官の苦悩を鋭く描いている。
主人公が先代である父に、展覧会のための作品を焼きたいと願う場面がある。先代は「芸術家になりたいか」と一蹴するのだが、それに続く文章を引用してみよう。
・・・この父親の言葉が不服であった。「それではいったい」と現当主は泣くようにいった。「自分というものは何のために生きているのでしょう」。沈氏は、いった。哀れすぎるではないか。あなたもおそらく若いころに家とこの家芸を継がねばならぬと悩まれたと思うが、いったい自分はなにを目標に生きていけばよいのか、それを聞かせてほしい、といった。現当主は少年のころ、この父親から英語も数学も教わり、さらに少年のころから作陶の技術を教わった。つねに師であった。三十を過ぎ、かれ自身も子をもつようになってからこの父親の偉さが一年ごとにすこしずつわかりはじめている。
現当主は「教えてたもし」と、懇願した。十三代翁は、ひとことだけ言った。このひとことに、十三代翁自身の生涯の哀歓が煮詰まっていたであろう。「息子をちゃわん屋にせいや」わしの役目はそれだけしかなかったし、お前の役目もそれだけでしかない、といった。
短編とはいえ歴史の悠久を流れに、ある時は翻弄され、ある時は抗う人間像に迫り、強い印象を残す。
司馬遼太郎の小説は大きく『梟の城』や『国盗り物語』などの時代物と、『竜馬がゆく』をはじめとする幕末維新物に分けることができる。前者は娯楽色が強いが、後者は司馬の歴史観が色濃くなる。筆者が小説に期待するのは、まずは面白いことで時代ものは合致するが、幕末維新物はちょっと面倒というのが、率直な感想である。
司馬が歴史的人物を描く場合、自身の調査内容や感想を書くことがあるが、そこに主観が入り込む。とくに、それが多いと感じたのが討幕軍の軍事戦略家の大村益次郎を主人公とした『花神』である。小説では大村益次郎がはじめて桂小五郎と面会した時、竹島(独島)のことを持ち出すのだが、司馬遼太郎は次のような説明を加えている。
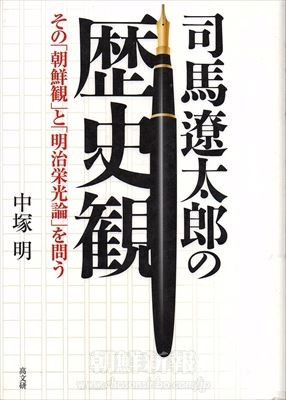
『司馬遼太郎の歴史観』
「この島の存在は豊臣期に発見され山陰地方の漁民が漁場としてひらいた。島には水がなく、人の居住をゆるさないが漁場としての価値が大きい。が、いったいこの無人島が日本のものであるのか韓国のものであるのか帰属がはっきりせず、江戸初期、日韓外交の一課題としてしばしば揉め、明治38年やっと日本領となり、島根県隠岐郡に属したが、第二次世界大戦後、ふたたびややこしくなり、韓国が主権を主張し、いまなお両国の間で未解決の課題となっている。」
現在、独島の帰属が政治問題となっているのは周知の事実であるが、この文章を読んだ人はどのように理解するだろうか? 独島が日本の領土であるにもかかわらず、戦後に朝鮮側が問題を持ち出したと思うに違いない。明治38年とは1905年で、「乙巳条約」が締結され朝鮮の外交権が奪われた年である。独島に関する朝鮮側の記録には触れることなく、その歴史的背景をまったく無視して日本領となったとする記述はあまりも一方的で、人気作家ゆえにその影響は大きい。
実は、筆者がこの『花神』に関心を持ったのは、靖国神社をどのように記述しているのかを知りたかったからである。靖国神社が侵略戦争に若い人を駆り立てる装置として機能したことは周知の事実であるが、元々は幕末維新の人物を祀る神社で、鳥居を入ったすぐのところに大村益次郎の銅像がある。ところが、小説ではまったく触れられていなかった。いや、むしろ「戦前の昭和は本来の姿ではなかった」とする司馬が、「栄光の明治」の立役者で日本の近代兵制を確立したとされる大村益次郎の銅像がそこにあることを説明しない、あるいはできないのは当然のことかもしれない。司馬は自身の史観にとって都合の悪い話には触れないのである。
これはほんの一例であるが、その典型ともいえるのが日清・日露戦争を描いた『坂の上の雲』である。朝鮮の覇権をめぐる戦争であったにもかかわらず、朝鮮農民軍の蜂起や抗日闘争についてはほとんど触れられていない。以前、NHKBSは『坂の上の雲』を3年にわたり放映したが、「司馬史観」が垂れ流されることに危惧を抱いた歴史家・中塚明は2009年に高文研から『司馬遼太郎の歴史観―その「朝鮮観」と「明治栄光論」を問う―』を出版した。『坂の上の雲』だけでなく『韓のくに紀行』の文章を引用しながら問題点を指摘しているが、朝鮮王朝時代には貨幣はなかったとする事実誤認や、農村は上代のままに停滞しているとする記述をはじめ、正直、司馬の「朝鮮観」はこんなに偏っていたのかと思わざるをえなかった。
小説に限らず様々な本に書かれていることや、日々のマスコミ報道に接する時に、それに流されぬようしっかりとした視点を持たなければと改めて思う。
(朝大理工学部講師)



